2023.03.02「自然治癒力の原典」
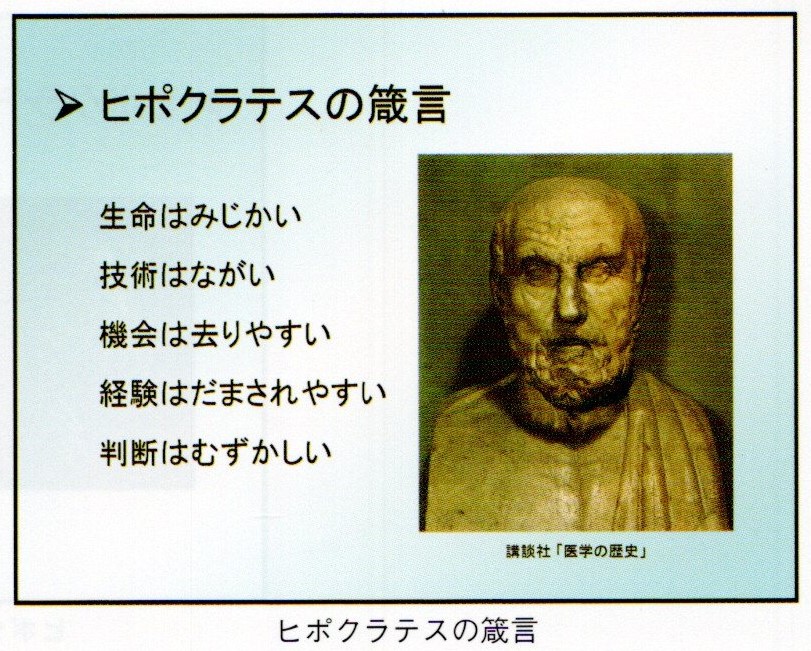
イトオテルミーの説明には必ず「自然治癒力」という単語が使われます。「自然治癒力」という言葉は漢字で構成されていることから中国由来の言葉だと誤解される方が多いと思います。実はこの言葉は古代ギリシャの哲学者ヒポクラテスがその概念を提唱し、オランダ語を通じて江戸時代の末期に日本に入ってきた概念を日本人が直接日本語に翻訳して出来た言葉です。そのときは自然作用力(テンネンノハタラキ)、自然良能と訳されて、最終的に一般的に「自然治癒力」という単語になりました。
したがってこの概念は東洋医学というよりは西洋の哲学に由来する日本独自のものなのです。
ヒポクラテスは「自然治癒力」の思想を次のように表しています。
①医療の主体は痛み苦しんでいる患者である
②病気は健康に至る肯定的な現象である
③自然治癒力は普段の養生によって保たれる
④治療に際しては自然治癒力を傷つけず、過剰な技術的介入をすべきではない
さて、イトオテルミーはヒポクラテスの「自然治癒力」に完全に沿った療法であるといえます。
①優しい温熱は患者の苦しみ、痛みを取り除く
②病気(炎症、免疫反応、下痢、嘔吐、発汗、発熱)自体も自然治癒力が働いている証拠なので、これを邪魔せずに楽にするテルミーは自然治癒力を促進している
③病気でない時もテルミーを習慣にしていれば、血液、リンパ、ホルモンが調和して流動するので病気になりにくい身体が出来る
④近代西洋医学のように悪いところ(病気の元)を取り除く、切り取るといった考えだけに固執せず、上の1~3を強化しながら自然治癒力がうまく働くように誘導することで、病気を治療することが大切である
ヒポクラテスは紀元前400年頃の人物ですが、中国では西暦1000年頃、初めて「未病」という言葉を使い始めました。未病とは病気になる前の前駆体(自然治癒力のバランスが崩れ始めて病気になりそうな状態)です。この状態は「生気」と「邪気」が戦って「邪気」が勝ちそうな状態のことです。この「生気」というのがヒポクラテスのいう「自然治癒力」ということが出来ます。
中国の考えはヒポクラテスの思想を1000年以上後から追いかけてやっとその足下に追いついたようなものです。
その後の日本における「自然治癒力」の発展については別の機会にお話しします。
引用:医剣宗一途 (伊藤元明 著)